
アレクサンダーさんの場合
2024年03月12日 22:59
今日は、アレクサンダー・テクニークが、いかに「止まる」ワークであるかということを説明していきます。
アレクサンダー・テクニークの創始者は、F.Mアレクサンダーさんという今から155年ほど前のオーストラリア出身の方です。アレクサンダーさんは、舞台上でシェークスピアの劇などを「朗誦」するお仕事をしていましたが、そのうち、舞台に立つたびに、声を失っていくという不調に見舞われました。
医者に勧められた通り、少しの間声を休めたりすると声は戻ってくるのですが、また舞台に立つ不調に陥る。
これは、
「自分でしている何かが、自分の機能を失わせているに違いない!」
と考えた彼は、三面鏡の前で、非常に長い間、何年もかけて自分が声を出す様子を観察したと言われています。それも、1日に何時間も。
その結果彼は、ある重要なことに気づきました。
それは、彼が「声を出そう!」と意図した瞬間、まだ声を出してもいないのに、その刺激に反応して、
首を「後ろに下に」押し下げていた
ということでした。
そして、その押し下げが起きることで、体の他の部分もロックがかかっていくようにあちこち硬くなる。
でも、その押し下げが起きないと、体は全体的に楽に、自由に動くことができる。
そういうことが、観察の結果分かったのです。
つまりは、その「首の押し下げ」が起きない状態で、「声を出す」という行為に移行することができれば、自分の機能が阻害されることがなく、声を失うということにもつながらないんじゃないか?と、彼は考えたわけです。
つまり、ここで、「止まる」という可能性と重要性が浮上してくるわけですね。
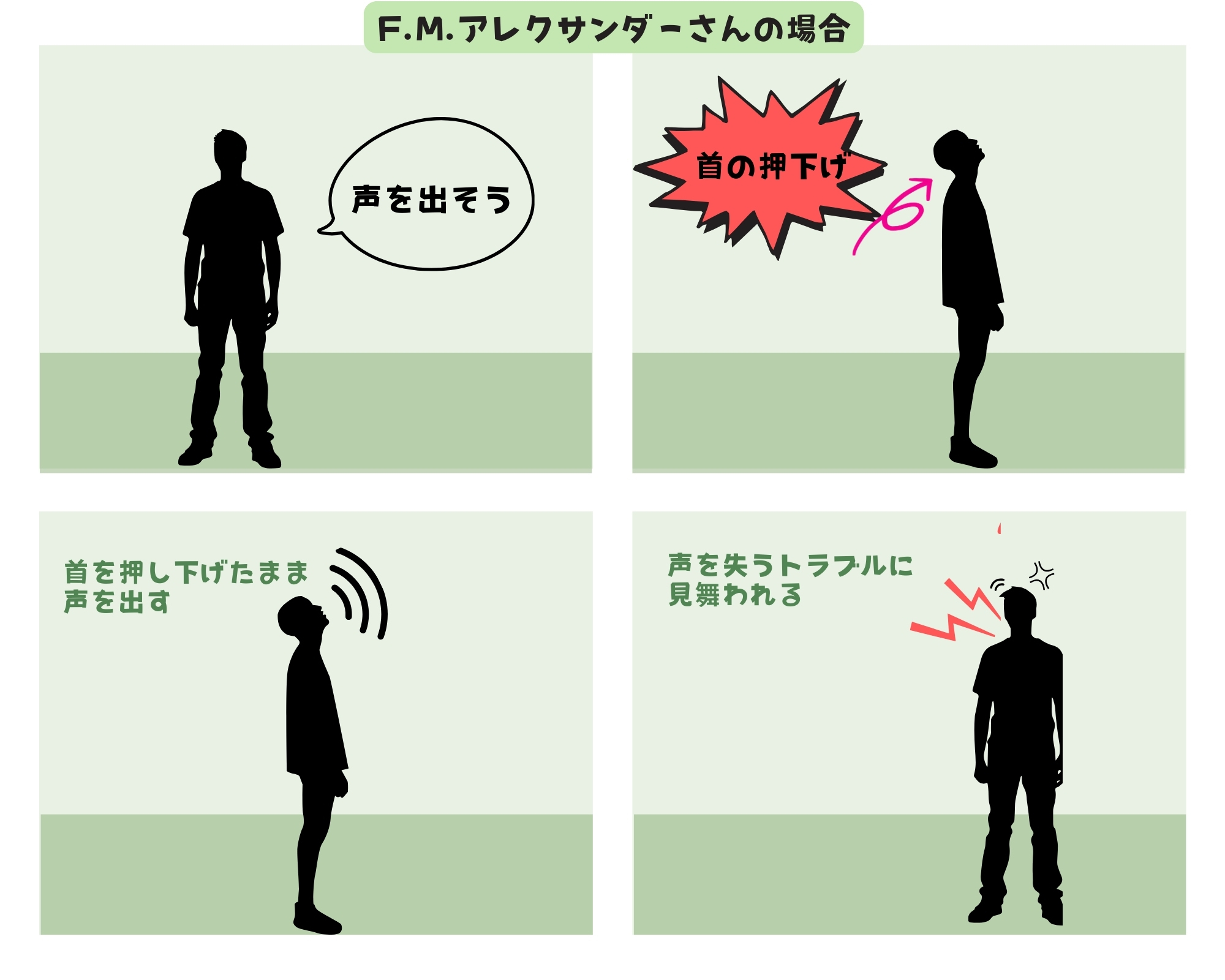 では一体、いつ、どのタイミングで止まったら、「首の押し下げ」が起きなくて済むのでしょうか?
では一体、いつ、どのタイミングで止まったら、「首の押し下げ」が起きなくて済むのでしょうか?
先ほど、彼は「声を出そう!」(A:意図を持つ)と思ったら、まだ「声を出す」という行為(B:行為の実践)には移行していないのに、「首の押し下げ」が起こっていたことを発見したと書きましたね。
つまりは、
Aの「○○をする意図を持つ」
ということと、
Bの「実際の行為をする」
間に、「止まる」必要があるということだったのです。
これに気づいてから、アレクサンダーさんは、更にさまざまな実験を繰り返し、「首の押し下げ」という「無意識な習慣」に入る前に「止まり」、別の思考をする重要性を発見したのです。
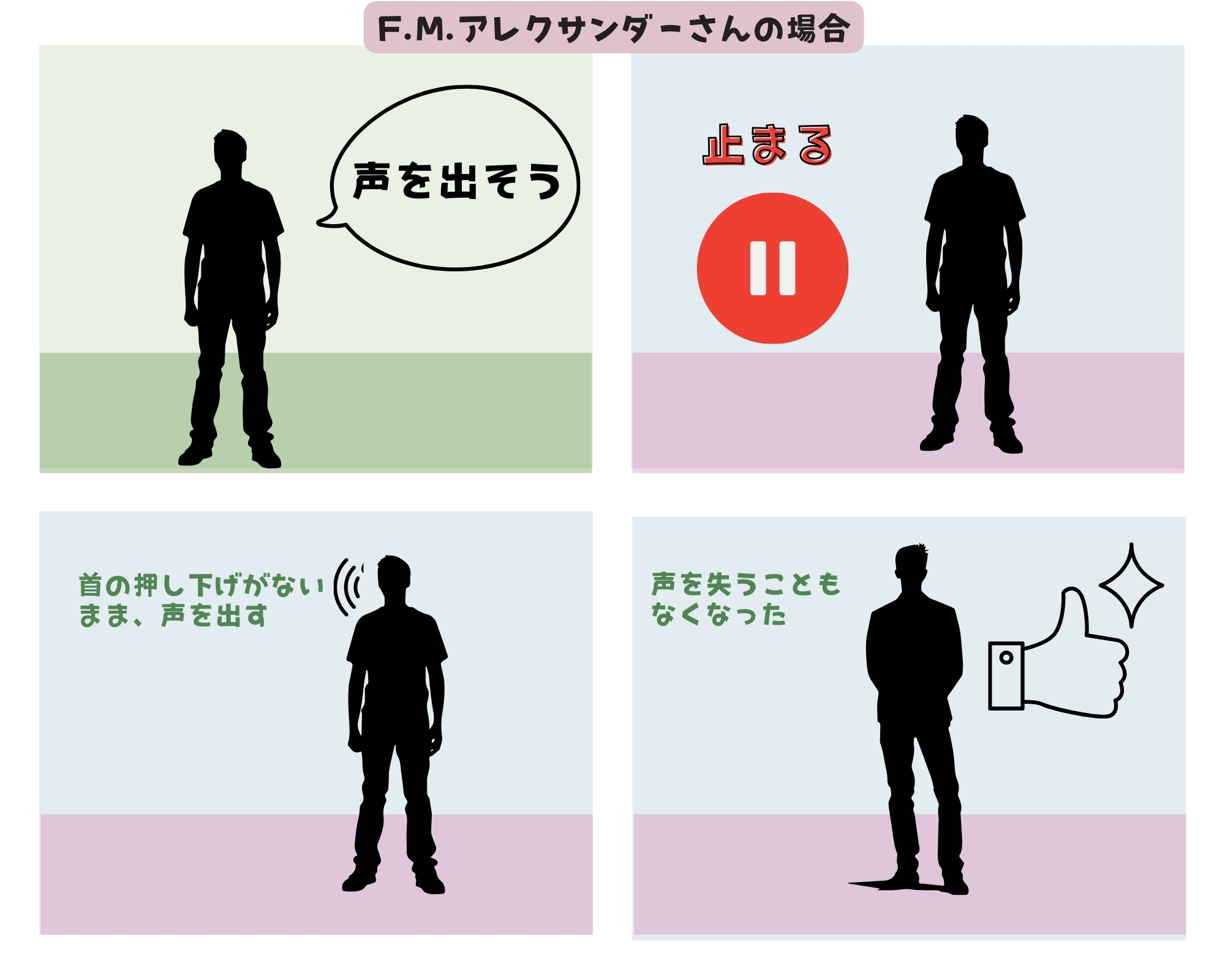
次回以降、私が実践しているPrimal Alexander™️のアプローチでの「止まる」ことの定義や、HSP(Highly Sensitive Person)が「止まる」ことで、どんな風に変われるのか、具体例などにも触れながら、お伝えしていきますね。
=====
「止まる」技を学ぶには、まずは自分のお悩み診断を!
